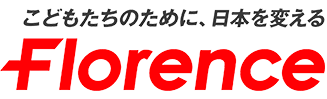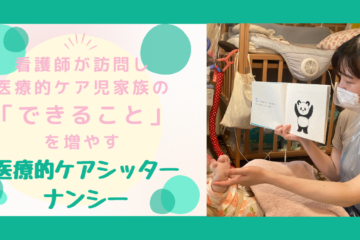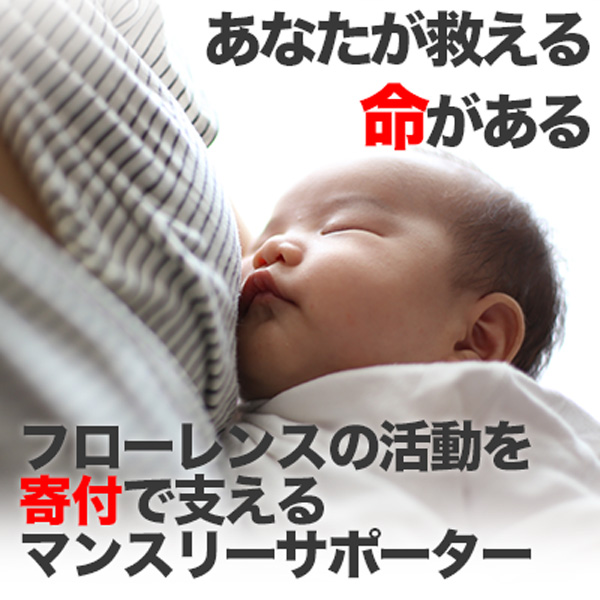2023/09/25
今までのあたりまえにとらわれず、未来の保育を考え、実践する“保育現場のイノベーション”の事例を紹介!
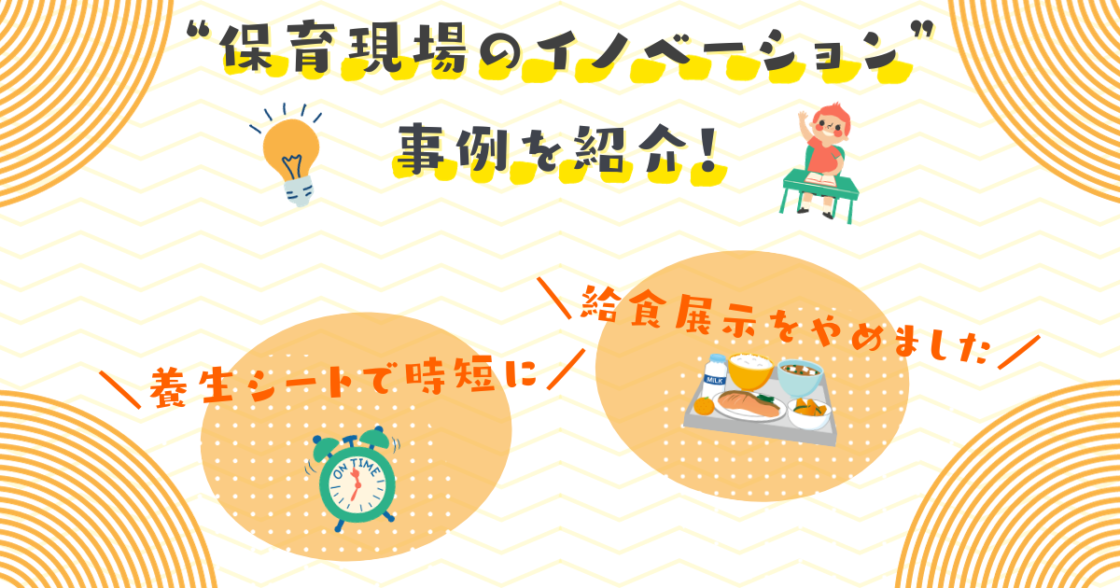
フローレンスの保育園は、子どもたちの「やってみたい」を応援するとともに、保育者自身のあたりまえや保育業界のあたりまえを疑い、日々の業務の改善や、 保育者のやってみたいからでた挑戦が溢れています。
「子どもたちにとって、私たちにとって、より良い未来になるためにはどうしたら良いのだろう…」
毎日のコツコツ地道な改善の積み重ね、ピンチをチャンスと捉える前向きな姿勢、仲間を信頼し、チームの力を信じること、そういった行動が、新しいあたりまえを作り出すイノベーションにつながるのではないでしょうか?
“新しいあたりまえを作り出すとか、イノベーションって、そんなすごいことできるの…?”
たしかに、イノベーションというと少し大げさかもしれませんが、「これをこんな風にしたら子どもたちと関わる時間がもっと増えるのに…」「こうしたら、子どもたちにとっても良い経験になるかもしれない!」と日々の保育の中で感じていることは皆さんの中にもたくさんあるのではないでしょうか?
保育者一人ひとりが「子どもにとってより良いことは何か?」を考え、自分の意見や価値観を保育者同士で共有し、より良い保育を実践するために日々チームで話し合い、その結果としていろいろな新しいあたりまえが作り出されています。
そこで、保育現場の新しいあたりまえの取り組みをご紹介します!
園児の疑問から生まれた新しいあたりまえ
‐どんな新しいあたりまえを作り出したのですか?そのきっかけを教えてください!

なり先生:
4~5年前の取り組みを紹介しますね!
給食の展示をしている保育園って多いと思うのですが、子どもたちの声を受けて展示をやめることにしました!
「これは捨てちゃうの?この後どうしているの?」「誰も食べないのにもったいないね…」という声があがったんです。あたりまえのように展示を続けていましたが、「なるほど!」と思いましたね!
‐すぐに展示をやめたのですか?
 ‐なり先生:
‐なり先生:
まず、保護者からも意見を聞きました。給食の展示はそもそも給食を見られない保護者のために置いていたものでした。園児が展示された給食をその後どうするのかを気にしていることを伝え、考えてもらいました。とくに離乳食の時期の家庭や、少食の園児の家庭、子どもの食事作りにヒントがほしい家庭などは参考にしてくれていたので。もちろん意見は様々でした。
そもそも、その意見をくれた園児の家庭は「この給食は誰が食べるの」と聞かれて困ったそうです。「先生が食べるのかな」などとお茶を濁し、時間が経っている展示の給食が廃棄されるとは子どもには言えなかったそうです。食材についても調理についても作ってくれた人に感謝の気持がある園や、そういう気持ちのある家庭の子どもが通う園は展示をやめるのが自然なことだったかもしれません。
しかし、大人たちは、園児のその一言がなかったら気づかなかった、と言えるでしょう。園児や保護者が声に出してくれる園であることが嬉しい出来事でした。
‐展示をやめたことで子どもたちの反応はどうでしたか?
 ‐なり先生:
‐なり先生:
とくに大きな反応はありません。意見を出してくれた園児はきっと「納得」という感じでしょうか。自分たちは毎日美味しい給食を目にして食べることができますから。
でも、その園児は「あれは誰が食べるんだろう」「降園時刻までずっと置いてある」「家の人と今日はこういう給食だったと話せるのはいいことだけど」「この給食はこのあとどうなるのだろう」という素朴な疑問があったのでしょう。
そして給食は無駄にしたくない、苦手なものもたまにあるけれど、皆で大事に食べたいという思いがあたりまえに根付いていたのでしょう。現在は連絡帳アプリのお知らせに給食の写真が掲載されています。

~給食の展示ケースは子どもたちの作品飾って活用~
‐保育者・子どもたちが共に未来を作っていくということが体現されている事例ですね!
子どもたち、そして保育者の「やってみたい!」を応援するために、心がけていることや大切にしていることはありますか?
 ‐なり先生:
‐なり先生:
大人も子どもも園の参加者である人が言ってくれたことは前例がなくても、これまで恒例としてきたこともなくしてもいい、前例がないこともやってみてもいい、としてます。そして、実現しようと決めたことは実現する、小さな有言実行を大切にしています。
「『ちょっと待っててね』の時間を少しでも減らしたい!」が業務改善に…!
‐どんな新しいあたりまえを実現したのか教えてください!

まさよ先生:離乳食テーブルの下にテープ付きの養生シートを利用することにしたんです!
以前まではブルーシートを利用していて、食事が終わった後、拭いて乾かして畳んで…という工程があったのですが、テープ付きの養生シートは、そのまま剥がして捨てることが可能なので、業務軽減につながりました。
ボロボロの雑巾をずっと使うより、業務用の紙ウェス(※紙製の雑巾のこと。使い捨てなので、衛生面でも使いやすいことが特徴)で2~3回使ったらポイで!など、小さいことですが「うちの園はこうしていく」という意識付けの一つとしてやっています。

~離乳食テーブルの下にマスカーテープを敷くことで業務改善に!~
‐確かにそれは業務軽減が実現された素晴らしい事例ですね!「やってみよう!」となったきっかけを教えてください。
 ‐まさよ先生:
‐まさよ先生:
大前提として「子ども一人ひとりと向き合うこと」を大切にしていることですね。
保育の中心は子ども自身。
子どもがどんなことを感じているのか、どんなことを考えているのか、どんなことをするのか、子どもに寄り添い、子どもの可能性を引き出す保育を実現するにはどうしたら良いか?を第一に考えていると、私たち大人も「こんなことやってみたい!」「こうしたら良いんじゃない?」という声が自然と出てきます。
「ちょっと待っててね」という時間を少しでも減らしたいですから。
それが業務軽減につながっているという感じですね!
もちろん、業務軽減できたら…と思うことはたくさんありますが、業務軽減を第一に考えているわけではなく、子どもたちにとってより良い保育を実現するためには?ということを常に考えています。
‐この取り組みによってどんな変化がありましたか?
 ‐まさよ先生:
‐まさよ先生:
実は「これはやめたら」という提案がすべてのスタッフの納得感を得られているかといえばわかりません(笑)。年度終わりの制作帳にしても、1年間の制作物を園で保管してまとめて表紙をつけて・・それはそれで、思い出に残るゴージャスなものをこれまで作ってきて保護者や子どもたちが喜んでくれたという充実感みたいなものが絶対あると思います。(私も味わってきました)
でも、本来、園の「製作」って「作品集」が最終目的ではなくて、「体験」であり、季節の行事を知るツールの1つで“そのとき”に作ったものをお家で楽しむことも目的だと考えます。
それで、3月の年度末に製作帳としてイチから作るのをやめて作品は写真で保管して市販のフォトブックに入れ、個人のアルバム風にしました。(他園でもやっている取り組みです)作業は0ではありませんが、かなり削減されたと思っています。
あと、最近ですが、指導計画作成についても、区の方針に沿いながらも簡素化できることがわかり、作成するものを絞り込むことにしました。これまで丁寧にきちんと書いてきたスタッフにとっては「ほんとにこれでいいの?」「自分としてはこれまで通りでやりたい」と思っているかもしれません。でも、書類作成が残業になったり、負担になることもままあることを考えれば、これも子どもと向き合うことを大切に、という視点につながるのではにないかと思っています。
‐「こんなことやってみたい!「こんな風にしたら良いんじゃない?」というものに対して、反対することはないのでしょうか?
 ‐まさよ先生:
‐まさよ先生:
そのような思いや挑戦が出てくるのは、子どものやりたい!という気持ちをどう実現させていくか、子どもたちにとってより良いことは何かに真剣に向き合っているからですよね!
目まぐるしく変化する社会の中で「保育はこうあるべきだ」という正解ってないと思うんです。
子どものことを思い、寄り添ったものであれば反対することはないですね。
スタッフのバックグラウンドも多様なので、チームで話し合うことによって新たな気づきを得ることもたくさんあります。「子どもにとって」「みんなにとって」より良いことをチームで考えるということも大切にしています。
いかがでしたか?
フローレンスの保育園は、「子どもたちにとって」を大切にし、新しい可能性を生み出せるチームを目指しています。ぜひ私たちと一緒により良いみらいを作っていきませんか。
フローレンスでは、社会問題や働き方など、これからもさまざまなコンテンツを発信していきます。
ぜひ、SNSもフォローしてください!
もしかしたら、SNSでしか見れない情報もあるかも!?気になるアイコンをタップ!
その他のフローレンスNEWSはこちら
-
2024.07.26
自分らしくいられる保育園【みんなのみらいをつくる保育園東雲】~「意見が違っても友達だよね」こども自身が対話する取り組み「サークルタイム」~ NEW!
-
2024.07.25
-
2024.07.19